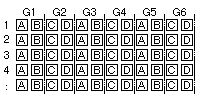フルドットマトリクスタイプ
フルドットマトリクスのMNシリーズの場合は、VFD独特の特殊な駆動原理をご理解いただく必要があります。 以下の情報がそのご理解の手助けとなれば幸いです。
まずMNシリーズですが、ドライバやアノードの構成上、以下の表のように4つの種類に分類することができます。
表3 MNシリーズの分類
| 区分 | ドライバ | アノード分割 | 標準品種(98年8月現在) |
| (1) | グリッド/アノード 混成タイプ |
4分割 | なし |
| (2) | 8分割 | MN12808B、MN12818A/AB | |
| (3) | グリッド/アノード 独立タイプ |
4分割 | MN12832E/EC、MN12864H、MN16016F、MN25664D |
| (4) | 8分割 | MN19216G、MN25616P |
グリッド/アノード混成ドライバタイプ
MNシリーズのグリッド/アノード混成ドライバの場合、アノード4分割タイプでも8分割タイプでも、 データ転送の概念としては4.2.1項にある一般的なグリッド/アノード混成ドライバと原則的に同じです。 ただMNシリーズの場合は、フルドットマトリクスですので、重なりグリッドスキャンという手法を用いることになります。 同時に2つのグリッドを選択して点灯させたり、その時点灯(選択)できるアノードグループに制約があるなど、 かなり特殊なルールがありますので、個別の仕様書をよくご覧ください。
グリッド/アノード独立ドライバタイプ
MNシリーズのグリッド/アノード独立ドライバタイプの場合は、 3系統のシリアルポートによってそれぞれグリッドスキャンとアノードデータのコントロールを行います。 グリッドはグリッド専用の独立したドライバが、アノードのは2つのアノードドライバでグループを分担して駆動します。 アノード4分割のタイプ(3)の場合は、ドライバ1がAとDアノードを、ドライバ2がBとCアノードを専門に、 またアノード8分割のタイプ(4)の場合は、ドライバ1がa、b、g、hアノードを、 ドライバ2がc、d、e、fアノードをそれぞれ専門に駆動します。
表4 グリッド/アノード独立ドライバタイプのアノードドライバ
| 区分 | アノード分割 | アノードドライバ1 | アノードドライバ2 | グリッドアノード割り当て |
| (3) | 4分割 A/B/C/D |
A、Dアノード を駆動 |
B、Cアノード を駆動 |
|
| (4) | 8分割 a/b/c/d e/f/g/h |
a、b、g、h アノードを駆動 |
c、d、e、f アノードを駆動 |
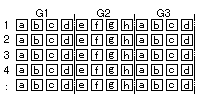 |
グリッド/アノード独立ドライバタイプの駆動方法
以下の表とタイミングチャートはグリッド/アノード独立ドライバタイプのMNシリーズを駆動する例です。
表5 グリッドスキャンとアノードデータコントロールの例(MN12832E)
| タイミング |
オンする グリッド |
グリッドドライバ出力 |
アノード ブランキング |
選択できる アノード |
|||||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ...... | G60 | G61 | G62 | G63 | G64 | BK1 | BK2 | SI1/SI2 | ||
| T64 | G63+G64 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | H | L | B、C |
| T1 | G64+G1 | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | H |
A、D |
| T2 | G1+G2 | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | B、C |
| T3 | G2+G3 | L | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | A、D |
| T4 | G3+G4 | L | L | H | H | L | L | L | L | L | L | L | H | L | B、C |
| T5 | G4+G5 | L | L | L | H | H | L | L | L | L | L | L | L | H | A、D |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| T61 | G60+G61 | L | L | L | L | L | L | H | H | L | L | L | L | H | A、D |
| T62 | G61+G62 | L | L | L | L | L | L | L | H | H | L | L | H | L | B、C |
| T63 | G62+G63 | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | L | L | H | A、D |
| T64 | G63+G64 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | H | L | B、C |
| T1 | G64+G1 | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | H | A、D |
グリッドスキャン
グリッド/アノード独立ドライバタイプの場合、図17dのように、LATGをハイレベル(H)に固定し、 桁間ブランキングの間にCLKGへ1つのクロックパルスを送ることによって、 グリッドスキャンを自動的に行わせることが可能です。
SIGはT64とT1、T1とT2の桁間ブランキング間にCLKGのパルスを送る時のみハイレベル(H)にセットし、 その他のタイミングではローレベル(L)にします。
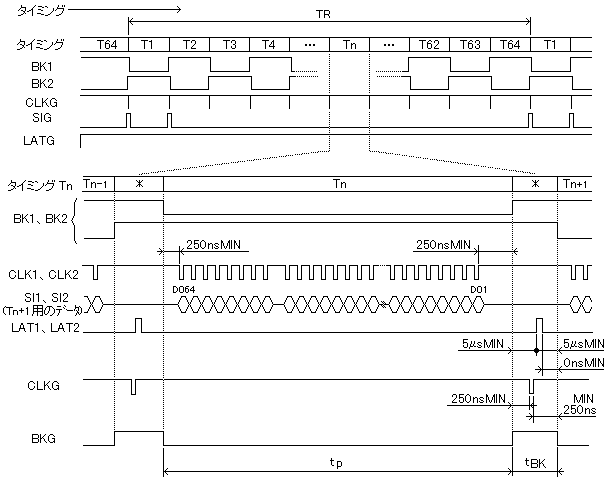
図17d MN12832Eのタイミングチャート
アノードデータとBK1、BK2
まずSI1とSI2ですが、これらは図17eのように回路上で接続しておきます。 例えばタイミングT2ではグリッドG1とG2の2つのグリッドを選択(オン)します。 T2ではアノードドライバ2はBK2をロー(L)にすることによってアクティブに、 逆にアノードドライバ1はBK1をハイ(H)にしてインアクティブの状態にそれぞれセットします。 T2で選択できるアノードは、グリッドG1とG2の中にあるアノードBおよびCグループのみで、 アノードAとDについてはこの時は無視します。 実際には、タイミングT2で点灯するBとCのアノードデータ(オン=H、オフ=L)は、 タイミングT1の間にシフトレジスタに送っておきます。 SI1とSI2は回路上で接続しておきますので、 当然アノードドライバ2と同じデータがアノードドライバ1のシフトレジスタに入り込むことになりますが、 アノードドライバ1はタイミングT2ではインアクティブの状態になるので、AとDのアノードは全てオフとなります。
次のタイミングT3ではG2とG3が選択され、G2とG3の中にあるAとDアノードを点灯します。 この時先ほどのT2とは逆に、アノードドライバ1をBK1をロー(L)にすることによってアクティブに、 アノードドライバ2はBK2をハイ(H)にしてインアクティブの状態にセットします。 もちろんAとDのアノードデータはT2のタイミングの時に転送しておきます。
表6は表中右にあるようなドットを点灯させたい場合のデータ転送の例です。
駆動回路例
図17eはMN12832Eの駆動回路例です。
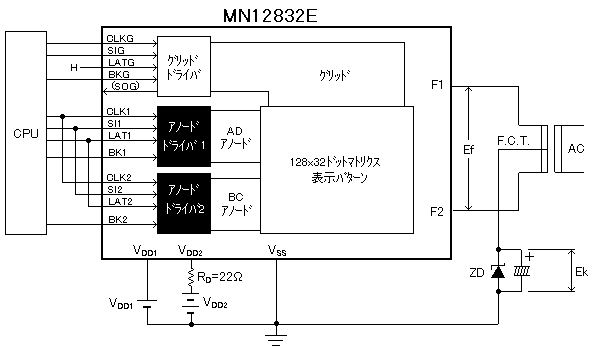
図17e MN12832Eの駆動回路例
ドライバ内蔵型BD-VFD アプリケーションノート
-
BD-VFDの構造
-
BD-VFDの電源
-
BD-VFDのインターフェース
-
BD-VFDの駆動方法
-
デザインガイダンス
-
その他