蛍光表示管の原理
蛍光表示管(VFD)はノリタケ伊勢電子(旧:伊勢電子工業)が1966年に世界で初めて開発した日本生まれのユニークな表示素子です。 蛍光表示管は、電子の信号を人が見える光に変える働きをします。 コンピュータなどから出る信号を人に伝えるため、電子の信号で蛍光体を光らせ、数字、 漢字、かな、アルファベット、記号や図形などを表示します。
動作原理
その基本的な原理は、3極真空管で低速電子線により蛍光体を発光させるというユニークなものです。 駆動電圧が低く、低消費電力で高輝度が得られ、非常に美しく見やすいというすぐれた特性と特長を持っています。
蛍光表示管は、カソード、グリッドおよびアノードを高真空の箱型のガラス容器に封入したものです。 カソードは、タングステンの極細線にアルカリ土類金属の酸化物を塗布した、 直熱型カソード(フィラメント)です。グリッドは薄い金属メッシュです。 アノードは導体電極で互いに絶縁を保ったセグメント、ドット、あるいは記号で構成されています。 そのアノードの上に蛍光体が塗布されており、さまざまな形状にして発光させることができます。
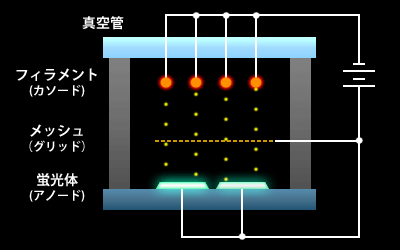
図1 蛍光表示管の動作原理
図1は蛍光表示管の動作原理を模式的に示すものです。 フィラメントは極細線で600度以上に熱すると電子が放出されます。 電子は、グリッドおよびアノードに印加したプラス電位に引き寄せられ加速されます。 加速された電子はアノードに塗布した蛍光体に衝突し、この時発光が起こります。 グリッドおよびアノードは選択的に電位を印加することにより、 任意の数字、文字、図形を自由に表示させることができます。
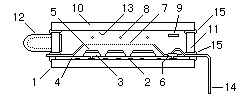
図2 蛍光表示管(排気管有)の断面図
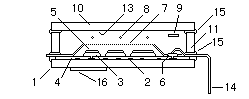
図3 蛍光表示管(排気管無)の断面図
| 1. プレートガラス | 5. 蛍光体 | 9. ゲッター | 13. 透明導電膜(ネサ) |
| 2. 導電層 | 6. 導電パッド | 10. フロントガラス | 14. リードピン |
| 3. アノード電極 | 7. グリッド | 11. スペーサガラス | 15. 封着ガラス(フリット) |
| 4. 絶縁層 | 8. フィラメント | 12. 排気管 | 16. 排気孔栓 |
VFD全般 アプリケーションノート
-
蛍光表示管の原理と構造(APF102)
-
蛍光表示管の信頼性と品質保証 (APF103)
-
蛍光表示管の取り扱いに関するお願い (APF104)
-
デザインガイダンス (APF101)
-
蛍光表示管の駆動方法 (APF201)
-
蛍光表示管の発光色とフィルタ (APF301)








